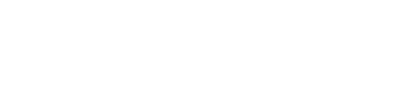- トップ
- 株主・投資家の皆様へ
- 統合報告書
- 社外取締役座談会
急速な変化の中、強みを生かした持続的成長を
自らの専門的な知見に基づく助言と、独立した立場からステークホルダーの皆様の意見を率直に伝えることで、取締役会の実効性向上に貢献する社外取締役。個性豊かな5名の社外取締役にお集まりいただき、当社グループのガバナンスにおける課題や中長期的な企業価値向上について活発な議論を交わしました。

鈴木 信哉
2017年6月より現職。
指名・報酬委員会委員長。長年、林業政策に携わり、森林・林業・木材産業に関わる専門的な知識と経験を有する。事業戦略に有益な提言をいただいている。

小久保 崇
2019 年6月より現職。
弁護士として企業法務、M&A、資金調達等に関する豊富な経験を有する。コーポレート・ガバナンス強化に貢献いただいている。

濱田 清仁
2019年6月より現職。
公認会計士及び税理士として専門的な知識と経験を有する。新規投資やM&A等を中心に、経営の健全性強化に貢献いただいている。

田村 潤
2020年6月より現職。
大手食品製造会社における経営、マーケティング、人事労務等の多様な経験を有する。グループの成長・発展に向けた提言をいただいている。

筧 悦子
2024年6月より現職。
ITによるトランスフォーメーションをリードした経験と知見を有する。DXやDE&I推進等のガバナンス強化に貢献いただいている。
取締役会の実効性評価と社外取締役としてのアプローチ
― 本日はお集まりいただきありがとうございます。まずは、取締役会における議論について全体的な評価をお聞かせください。
小久保:私が就任した当時、当社グループのガバナンスは、形式的に運用される傾向が強く、経営実態を十分に反映していないという印象を受けました。しかし最近は、現場の状況や経営陣の考えを踏まえた議論が増えつつあり、取締役会の実効性が伴ってきていると感じています。
鈴 木:既に方向性が明確な審議事項だけでなく、方向性が定まっていない、あるいは決めかねている事項についても、私たち社外取締役の意見が求められる場面が増えてきました。特に、当社グループは連結子会社が多いため、連結ベースの財務指標にも影響する子会社の経営実態や方向性に関する議論が始まったことは、前向きな変化だと感じています。
濱 田:私も、社内役員からの説明機会が増え、社外取締役の見解に耳を傾ける体制へと変化してきたことを評価しています。一方、経営の中枢にまで踏み込んだ深い議論がなされているかと言えば、そこにはまだ改善の余地があると感じます。より上位の視点を持って議論を深め、戦略的な意思決定の場として、取締役会の機能を強化することが必要です。
田 村:議論における意見が具体的な施策に反映され、実行に結びついているかという点でも課題があります。大局的な視点で戦略を立案し、その妥当性を取締役会で議論した上で、細部にまで落とし込む枠組みを整備する必要があると考えています。
筧 :議題については、短期的かつ設備投資等の有形資産に関連するものが中心ですが、中長期的な成長戦略や利益構造の転換に関するものへと軸足を移すべきです。中長期的な成長に向けて、市場分析等の客観的な裏付けに基づくディスカッションをもっと深め、取締役会を、経営戦略や投資方針に関する議論の場へとシフトさせていくことが重要であると考えています。
小久保:現状は、どちらかと言うとリスク管理やコンプライアンス等の「守り」の議論が多く、人材育成やブランド戦略など、無形資産への投資をはじめとする「攻め」の議論を活発化させていくことが必要です。当社は今、攻めの施策を実行に移すフェーズに入っており、経営判断のスピードと安全性のバランスが問われています。
― 中長期的な視点での議論の重要性が、共通の課題認識と言えるかと思います。実効性の向上についてはどのようにお考えでしょうか。
田 村:私は、合意形成や意思決定プロセスの明確化を、より強く求めていきたいと考えています。当社グループの社員は真面目な方が多く、現場では最終的な判断を上位者に委ねるケースが多く見受けられます。しかし、真面目な社員が多いからこそ、現場の社員が自律的に判断し責任を持って動ける環境整備が必要です。
濱 田:取締役会において、中長期的な視点で質の高い意思決定を行うには、潜在的なリスクや課題等を認識し、多角的な情報に基づいて議論することが不可欠です。そうした観点から、監査役会との連携を更に強化することが、実効性を高めるために有効であると考えています。
鈴 木:今後は、社内取締役がそれぞれの専門領域を超えて自由闊達に意見を交わすことを期待しています。戦略の一つとして他社との協業を進めるに当たっても、多様な視点に立ち、リスクや戦略を評価することが重要です。取締役会全体における議論が活発化し、戦略的な意思決定がなされるよう促していきたいと思います。
ナイスグループの強みを発揮し、企業価値を更に高めるために
― ボトムアップ型経営への変革を進める中で、更なる成長の原動力となるものは何だとお考えでしょうか。
鈴 木:急速な時代の変化を捉えて、迅速に対応することが、当社グループの中長期的な成長につながると考えています。木材・建材マーケットにおいては、新設住宅着工戸数が主要指標となりがちですが、今後の成長性を見極め、戦略を多角的に進めることが一層重要になってくるでしょう。その点では、中古住宅リフォームや非住宅建築物の木造化・木質化、住宅設備機器メーカーとのコラボレーションによる木質系商品開発など、今後当社グループが注力していく取り組みに期待しています。
田 村:当社グループの価値創出の源泉は、「信頼」を礎とする企業理念にあります。「信頼」と国産木材の供給力をはじめとする強みを磨き上げ、その強みを生かして市場での存在感を高めることが、持続的な成長につながります。そのためにも、企業理念を軸とした中長期戦略の意義を社員に浸透させ、現場の行動にまで落とし込むことが必要です。それにより、力強い実行力が生まれ、経営陣と社員とが一体となって価値を創造する企業文化を築けるはずです。
濱 田:提供価値が株価にもポジティブに反映されるには、投資家から見て明らかに「変わった」という印象を与えることが重要と考えています。その点、画期的な商品開発は社会へ大きなインパクトを与える可能性を秘めています。一例として、無垢国産木材を活用した「Gywood®」は新素材としての価値が高く、その将来性に大きな期待を抱いています。この素晴らしい価値を、社会に広く理解・浸透させるための戦略的なアプローチが必要です。また、生産体制の整備等の必要な投資を積極的に講じることが、更なる飛躍につながると確信しています。
筧 :既存事業の延長線上にあるビジネスだけでなく、イノベーションの視点から新規ビジネスに挑むことも重要です。市場や顧客にとっての価値を起点に強みを再定義することで、アプローチも多様化するのではないでしょうか。また、営業体制や商品・サービスの設計においても、業界や部門の常識に捉われず、柔軟な発想を取り入れることが求められます。ただし、これは若手や現場発信のアイデアを吸い上げる制度、更にトライ&エラーを許容できる組織風土の醸成なしには実現しません。今後、新たな価値創造に向けた組織的な仕掛けが必要だと考えています。
小久保:今、経営陣に必要なのは、社員が失敗を恐れず挑戦する意欲や創造性を育む、創意工夫のマネジメントです。業績等の成果ばかりを追求する短期的な管理では、人材は育ちません。社内ベンチャー制度や子会社単位のプロジェクトなど、様々なトライアルを推進することを期待しています。また、こうした変革に向けて提言していくことが、私たち社外取締役の役割だと認識しています。
筧 :社員も、これまでのキャリアで積み上げてきた既存のマネジメント手法に捉われず、外部の研修プログラムや他社とのコミュニティーに積極的に参加し、多様な知見や情報を吸収してほしいと思います。自社を客観的に捉える視点が、変化を恐れない勇気や柔軟性につながり、会社の変革と成長を牽引できる次世代のリーダーが育っていくと考えています。
濱 田:経営層への若い人材の積極的な引き上げも、会社の持続的な成長に不可欠と言えます。実践を通じてトライ&エラーの経験を積むことが、人材を育成する何よりの近道です。当社グループには優秀な若い人材が多数在籍しています。彼らにもっと責任と実践の場を与え、経験を通じて人材が育つ機会を創出していくことが重要です。
小久保:私も、グループ全体でビジネスアイデアコンテストを実施した際には、本社外の営業所や子会社にも優れた人材が確実にいると感じました。そうした人材の重要性は言うまでもありません。取り組みは一歩ずつ進んでいますが、グループ全体の活動として広がり、根付いていくことが重要です。今後の成長に向けては、グループの力を結集させた戦略連携が課題であり、可能性でもあると言えます。
鈴 木:加えて、既存の取引先との関係性にとどまらず、業界の垣根を超えた幅広い人脈を形成することにも大きな意義があると考えます。今後、新規事業や他社とのコラボレーションを進める上でも、人脈は貴重な財産になるはずです。様々な課題がありますが、まずは経営陣自らが方針に沿って模範となる行動をとることが重要です。
田 村:当社グループは2025 年に75 周年を迎え、今、100周年を目指して再び前進を始めたところです。これまで様々な100 年企業を見てきましたが、その企業に共通しているのは、アウトプットがどんどん変化している中でも、根本にある精神や理念が変わらず継承されているということです。当社グループも、時代の変化をチャンスと捉えて成長するためには、信頼を更に強化し、それを武器に打って出る姿勢が大切です。それが真のサステナビリティだと考えています。
最大の財産である人的資本を強化し、信頼と成果の両面で応える経営を
― 最後に、持続的な成長と進化に向けて、今後の期待と可能性についてお聞かせください。特に、人的資本の強化は、企業価値向上の鍵とも言えます。
鈴 木:当社グループの最大の財産は、お客様に真摯に向き合う全ての社員の内奥にあります。信頼を重視するこの精神は今後も大切にし、引き継がなければなりません。
田 村:社員の行動を見ていると、信頼に応えるという理念を、特別なものとしてではなく日常の延長として自然に受け入れていると感じます。当社グループは、「信頼」という価値観が文化として組織に深く根付いている数少ない企業と言えるのではないでしょうか。時代が短期的成果を求める傾向にある今だからこそ、当社グループのように揺るぎない信頼を経営の基盤に置く企業には重要な使命があると思います。
濱 田:これから事業戦略を実行していく社員こそが最大の成長ドライバーです。人的資本を強化していくことが、中長期的に企業価値を向上させる鍵となります。若手をはじめ、優れた人材の潜在能力を最大限に引き出すことが重要です。現状は組織の硬直化が見られ、人材の能力が十分に発揮されていないと感じる部分があります。若手を中心とした人材の育成と、適切でバランスの取れた配置により、この状況を打破し、組織の活性化が図られていくことを期待しています。
筧 :社員一人ひとりが真面目に職務を遂行する企業風土は、企業価値向上の土台です。その真面目さを最大限に生かすためには、組織が存在意義に沿った目標設定を行い、達成に向けてリーダーが率先して行動で示すと同時に、目標の意味を現場の社員に丁寧に説明することが重要です。説明すれば社員は理解し、実行に移す力を持っています。ビジョンと実行の架け橋となるリーダーシップが、当社グループをもう一段階成長させる原動力になると考えています。
小久保:あとは、グループが一丸となって引き続き全力で実行するのみです。「中期経営計画Road to 2030」で示した累進配当方針は、経営陣の決意を裏付ける株主へ向けた強力なコミットメントと言えるでしょう。事業成長と企業価値向上を目指し、全てのステークホルダーに対して、信頼と成果の両面で応えていく姿勢が求められています。
鈴 木:当社グループは、国産木材の市売りから始まり、現在では川上から川下までに事業領域を広げています。世界が地球温暖化という大きな問題に直面し、国産木材市場が拡大を続けている今、この広い事業範囲と全国各地にある取引先とのネットワークが、他社との差別化を支える競争力となります。トップランナーになれる資源を持っている会社ですから、これを最大限に活用し、社員一丸となってダッシュしていただきたいと思います。
― 本日は貴重なご意見をありがとうございました。