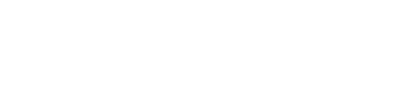ニュース&レポート
特別インタビュー 変化対応の経営 アイリスオーヤマ株式会社 代表取締役会長 大山 健太郎 氏
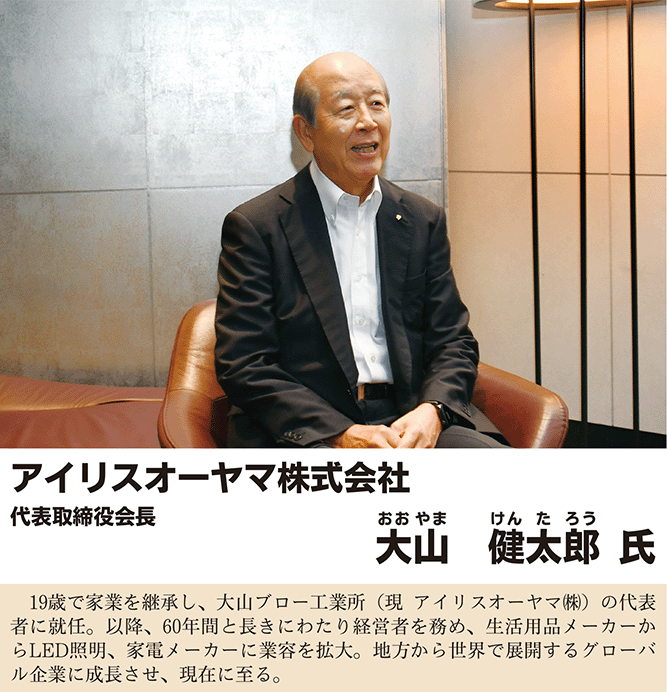
1971年に設立されたアイリスオーヤマ株式会社は、メーカーでありながら問屋の機能も有する独自の業態で、次々に新商品を開発する企画力により新たな市場を開拓し続けています。今回は、同社の大山健太郎会長に、スピード経営の秘訣や経営者としての考え方などについて伺いました。
産業資材メーカーとして急成長を遂げた創業期
―大山会長は60年以上もの間、経営者として第一線を走り続けてこられました。改めて、経営者になった当時のことについてお聞かせいただけますか。
大山 19歳の時に、父が経営していた大山ブロー工業所を引き継ぐ形で代表者に就任しました。当時は、東大阪市でプラスチック製品の下請け工場を営んでいましたが、下請けのままでは終わりたくないという強い思いがあり、当社の強みを生かしながら、当社の規模に合う方法で新商品を開発することから始めました。オリジナル商品の第1号は、海上養殖用のブイです。当時のブイはガラス製で破損しやすかったため、自在に成型できるプラスチック製にすることで安定性を高めました。
水産業の次に、同じく第一次産業の農業に着目しました。ちょうど田植え機が発明され、普及し始めた頃であり、規格サイズの稚苗を育てる育苗箱が必要でした。しかし、当時使われていた木製の育苗箱は耐久性に難があったため、寸法精度が高く、軽くて丈夫なプラスチック製の育苗箱の開発に取り組みました。「ブイ」と「育苗箱」のいずれの商品も瞬く間に普及し、大ヒットとなりました。
―現在本社を置く東北に新たに拠点を設けたのもこの頃ですね。
大山 水産業や農業の主なマーケットである東日本での受注が増えたことに伴い、需要に近い場所で商品を供給する生産拠点が必要になりました。そこで、東北地方の中でも物流網が発達し、年間降雪量の少ない宮城県に工場を新設し、大阪の本社と生産拠点を切り分けました。開発した商品は次々に大ヒットするなど、産業資材メーカーとして順風満帆に成長を続けていました。
会社の目的は永遠に存続すること
―オイルショックが大きな転換期になったと伺いました。
大山 当時、50年後に原油が枯渇するのではないかという話が広まったことで石油製品の需要が一時的に高まり、モノを作ればすぐに売れるという状態が続きました。当社においても、設備を増強して旺盛な需要に対応していました。プラスチックだけでなく、あらゆる製品に原油が使われていたため、ほとんどの産業がこの特殊な仮需要を経験しました。しかし、これまで採れなかった場所でも原油が採れるようになってくると一気に仮需要がなくなり、一転してモノが売れなくなってしまいました。過剰生産となり価格が一気に下がり、売れば売るほど赤字になるという事態に陥りました。10年かけて築き上げてきた会社の資産がたったの2年で底をつき、倒産寸前の状態まで追い込まれてしまいました。
―この時の経験をもとに、企業理念を策定されたそうですね。
大山 会社の目的は永遠に存続すること。企業理念に明文化されているこの一文は、オイルショックの経験を色濃く反映したものです(図1)。社員が安心して働き続けるためにも、会社は存続しなければなりません。会社を取り巻く環境は日々変化しているため、いかなる時代環境でも利益を出し続けるという強い意志を込めています。
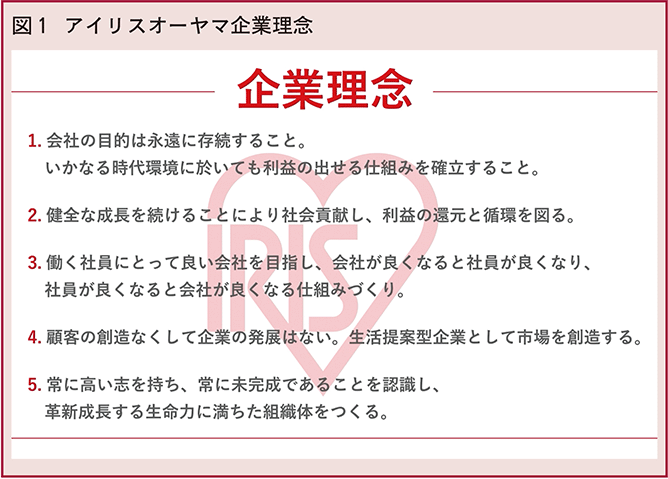
ユーザーインの発想で市場を創造
―オイルショックを機に、新たな業態へ転換されました。どのようなプロセスだったのでしょうか。
大山 オイルショックを踏まえて、何が間違っていたのかを考えました。私は、メーカーは技術力・価格競争力・シェアの三つがあれば衰退しないと考えていました。しかし、技術革新は時の流れとともに目まぐるしく変わっていくことを経験しました。そこで、プロダクトアウトの経営から脱却し、マーケットインの考え方に舵を切ることを検討しました。しかし、マーケットのニーズに合わせて商品を開発する場合、新規参入の企業には、低価格かつ高品質であることが求められます。生産拠点の宮城県から消費地である首都圏までの運搬コストを考えると、価格競争には勝てず、マーケットインの経営では生き残れないと判断しました。
そこで考えたのがユーザーインの発想です。これは、ユーザーの声に耳を傾けて商品開発することではありません。顕在化したニーズではなく、消費者もまだ気付いていない潜在的なニーズを発見し、需要を創造していくという考え方です。
―具体的にどのように需要を創造していったのでしょうか。
大山 私が着目したのは園芸用品でした。高度経済成長期にあり、生活が豊かになるにつれて、「庭をきれいにしたい」「室内で観葉植物を楽しみたい」というニーズが高まると考えたのです。そして何より、プラスチック製の育苗箱を開発した当社の強みを生かすことができる分野だと考えたからです。しかし、園芸用品は季節変動要因が大きいため、大手のスーパーマーケットでは売り場効率が良くないことを理由に扱ってもらえませんでした。そこで、当時急速な勢いで成長していたホームセンター業界に目を向けました。当時のホームセンターは、大量仕入れによる低価格販売を目指していたこともあり、商品調達に苦労していました。新たな道を歩み始めた当社にとって、ともに成長していくパートナーになり得ると考えたのです。ホームセンターは敷地が広く、店内ではなく屋外の売り場でも展開できるなど、比較的園芸用品を扱いやすいという利点もありました。プラスチック製のプランターや鉢、ホースリールといった商品を次々に開発し、ホームセンターで販売することで、ガーデニングブームをつくりあげました。
―ペットブームをけん引したのも貴社でした。
大山 当時、犬は番犬として外で飼われることが一般的で、ベニヤ板で作られた犬小屋が主流でしたが、時代の変化とともにペットも家族の一員であるという考え方が浸透していきました。そこで、犬が快適に過ごせる環境を作るためにプラスチック製のフェンスを開発しました。これによって、犬はフェンス内を自由に動き回ることができるようになりました。また、犬小屋についてもプラスチックの成型技術を生かして、水に強く、清潔で掃除も簡単な商品を開発し、爆発的にヒットしました。犬も家族の一員であるという目線で考えると、犬にも快適な生活をさせてあげたいという気持ちが強くなり、ペット用トイレやシーツ、室内用ハウスといった数々の商品化につながりました。
日々の生活の中で、こんなものがあったら便利で快適だという発想、まさにユーザーインの考え方で商品開発を進めています。
独自の業態「メーカーベンダーシステム」
―貴社の特長の一つであるメーカーベンダーシステムは、ホームセンターとの取り組みを通じて作られたと伺いました。
大山 ホームセンターを主な販売チャネルとして商品ラインアップを増やし、売り上げが伸びていくにつれて、ホームセンターからは問屋としての機能も求められるようになりました。ホームセンターでは、配送や陳列、店頭での広報活動に至るまで様々な機能を問屋が持っていたからです。考えた末に選択したのは、メーカーでありながら問屋としての機能を併せ持つ「メーカーベンダー」としての新しい業態でした。店頭活動にまで責任を持つとなれば、生活者の目線がますます大切になります。そして小売業の多様化する要望に応えるために、素材ありきの業種から、様々な素材とあらゆる技術を組み合わせて商品開発を行うビジネススタイルへ変化したのです。
―メーカーベンダーとなることで、どのようなメリットが生み出されたのでしょうか。
大山 問屋の機能も併せ持つことで、商流コストや物流コストを省きつつ、小売店のトレンドやニーズをタイムリーに把握することができます。また、商品を小売店にお届けするだけでなく、小売店の売り場をコンサルティングしながら魅力的な売り場づくりや販売促進のサポートも行うようになりました。すると、生活者の声がダイレクトにフィードバックされるようになり、生活者視点でオンリーワンの商品をスピーディーに開発することが可能となりました。このメーカーベンダーシステムが、アイリスオーヤマの強みの一つと言えます。
日本のニーズに応える「ジャパン・ソリューション」
―現在は、新たな経営の柱として「ジャパン・ソリューション」を掲げていらっしゃいます。
大山 大きな転換点となったのは、2011年に発生した東日本大震災です。被災直後、日本国内だけでなく海外のお取引先からも支援していただきました。そうした状況の中、当社はこのまま快適な生活を支えるだけの企業でよいのか自問自答しました。そしてたどり着いたのが、「ジャパン・ソリューション」という新たな経営の柱です。日本の課題に対して、当社ができる範囲で社会貢献しようということで、まず取り組んだのがLED照明による節電対策でした。福島第一原発の事故や計画停電という事態に直面し、節電は避けて通ることのできない命題であると感じ、震災後すぐに、私は工場のある中国・大連に向かいました。当社は、工場稼働率に3割のゆとりを持たせるフレキシブルな生産体制をとっており、その体制を生かしてLED照明の生産ラインを増強するよう指示しました。また、家庭用・法人用ともにLED照明の商品開発を加速させ、2011年だけでも実に1,000アイテムのLED照明を開発しました。現在では、日本だけでなく海外にもネットワークを拡大し、照明のLED化をグローバルに進めています。
―工場の稼働率にゆとりを持たせているのはなぜでしょうか。
大山 変化に迅速に対応することが大きな目的です。多くの企業は、顕在化している需要に対して稼働率を上げて生産性を高めています。需要が右肩上がりの時には確実に売り上げが伸びますが、需要に変化が生じた際には対応が遅れます。当社は、常に新しい需要をつくっているため、どのような結果になるのか予測が困難です。100売れると見込んでも、50しか売れない場合もあれば200以上売れる場合もあります。そのため、稼働率をあえて7割に抑えることで、変化が生じた際に迅速に対応できる体制としているのです。
―震災後、精米事業にも取り組まれています。
大山 東北の基盤は農業であり、特に米に関してはおいしく良質なブランド米が数多く生産されている地域です。しかし、農家を取り巻く環境は東日本大震災以降に厳しさを増し、高齢化が進む中で後継者不足にも直面しています。農業再生が東日本大震災からの復興につながるという思いのもと、農家の皆様のおいしい米を育てるノウハウと、当社のマーケティング力や製造技術、メーカーベンダーとして有するネットワークを組み合わせて、米の消費を拡大しようと考えました。ただし、おいしい新米も、月日が経てば風味が落ちてしまいます。その原因は、精米時に加わる熱と精米後の酸化でした。これを防ぐために、玄米の低温保管と低温環境下での精米・包装を行う「トータルコールド製法」という新しい精米技術を開発しました。そして、精米時の鮮度と風味を保つために、高気密性の小分けパックに窒素と脱酸素剤を封入した「新鮮小袋パック」方式を導入しました。これにより、東北で生産された米を全国に流通させることができたのです。今後は海外への輸出も視野に入れながら、日本の農業を世界に誇れる産業にしていきたいと考えています。
年間1,000アイテムを新たに開発
―年間1,000点以上の新商品を生み出すスピード戦略は、どのように実現されているのでしょうか。
大山 毎週月曜日に「新商品開発会議」を行っており、生活者目線で新商品に関するアイデアについて議論しています。当社が扱う商品は全てこの会議から生まれています。会議には、商品の立案者をはじめ、市場を調査するマーケティング担当、仕様を決める開発者、製造担当、取締役、そして最終的に決裁する社長が一堂に会し、情報を共有することでスピーディーな商品化につなげています(図2)。

一つの案件について5~10分で次々にプレゼンテーションが繰り広げられることから、この会議は「プレゼン会議」とも呼ばれています。また、このプレゼン会議ではあらゆる部門の人材が情報を共有し、企画が確定した段階から一斉にスタートする「伴走方式」も特長の一つです。そして何より、スピード開発の決め手となるのは即断即決の経営判断です。せっかくのアイデアも、経営陣が判断できなければ捨ててしまうことになります。価格や品質ももちろん大切ですが、結論を出す際の判断基準は「なるほど」と思わせるポイントがあるかどうかです。
―尽きないアイデアは、どこから生まれるのでしょうか。
大山 生活者にとっての不足、不満、不便はまだまだたくさんあります。私たちが開発しているのは、それらを解消する「ソリューション商品」なのです。開発に当たって最も大切にしていることは、開発者が自らの実体験に基づいて発想することです。生活者の声を聴くのではなく、自らも生活者の一人として料理や掃除をし、花を植え、ペットと暮らす中で、様々な不満や不便を発見し、商品開発につなげています。そして、より豊かな新しい生活ストーリーを思い描き、その実現に必要なものを連想することでアイデアを展開しているのです。これこそが、当社が大切にするユーザーインの発想なのです。
―最後に、大山会長が経営者として大切にしていらっしゃることについてお聞かせください。
大山 全ての新しいアイデアが成功するわけではないため、失敗のリスクを取らない限り新商品の開発はできません。ここで重要なことは、経営者が自ら判断し、その結果に対する責任も経営者が取ることです。これが、経営における基本だと考えています。だからこそ、判断をする際にはアイデアの発案者と直接対話しています。失敗したら経営者の責任、成功したら社員の手柄。これを徹底しているからこそ、当社では次々にアイデアが出てくるのです。
もう一つ、私が大切にしている考え方として、「NDD」があります。Nは「なぜ」、Dは「どうして」、もう一つのDが「どうすれば」。これを繰り返し考えることで、これまで前例のない経営戦略を打ち出して市場を開拓してきました。この考え方を軸にすることによって、目線が変わり、物事の本質が見えてくるのではないでしょうか。
―本日はありがとうございました。