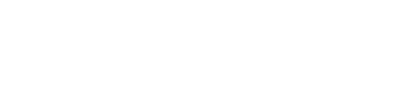ニュース&レポート
特別寄稿「木材・住宅市況を読む」③ 輸入木材の価格、その行方は? 価格を動かす「波」「潮」「うねり」から読み解く
森林・林業・環境経済を研究テーマとする㈱農林中金総合研究所の安藤範親氏による特別寄稿シリーズ「木材・住宅市況を読む」第3回です。近年、木材価格は大きく変動していますが、その価格は一体どのように決まるのでしょうか。本稿では、価格を動かす要因を、短期的な「波」、中長期的な「潮」、そして予測不能な「うねり」という三つの力に例え、今後の行方を読み解いていただきました。

株式会社農林中金総合研究所 主任研究員 安藤 範親 氏
木材価格を動かす三つの力
住宅や家具など、私たちの暮らしに欠かせない木材。その多くは海外からの輸入に頼っており、その価格は私たちの生活にも静かに影響を及ぼしています。近年、木材価格が大きく変動するニュースを目にする機会が増えましたが、一体どのような仕組みで価格は決まっているのでしょうか。
日本の木材の輸入価格は、複雑な要因が絡み合って形成されます。為替レートや海上運賃といった短期的な「波」、世界各国の住宅市場といった数ヶ月から年単位で価格の基調を左右する中長期的な「潮」が存在します。さらに近年、米国の通商政策に代表されるような、予測が難しい「うねり」が、世界の木材フローに新たな影響を及ぼし始めています。
なお、ここでの分析は過去のデータから見られる傾向を基にした一つの考え方です。世界情勢の変化といった大きな「うねり」は、これまでのパターンを覆す可能性があることを、あらかじめご留意ください。
価格を動かす短期的な「波」-為替と海上運賃
輸入木材の価格に最も早く、直接的に影響を与えるのが「為替レート」と「海上運賃」です。これらは、常に変動する海の「波」に似ています。
木材の国際取引は、多くが米ドルで行われます。そのため、円安が進むと、海外で同じ価格の木材を買うために、より多くの円が必要になります。つまり、円安は日本の輸入価格を押し上げる大きな要因となります。
次に、輸入木材は海外から船で運ばれてきます。船の運賃が上がれば、当然そのコストが木材価格に上乗せされます。コロナ禍でコンテナ不足が深刻化した際には、運賃が数倍に跳ね上がり、木材価格を高騰させました。足元では運賃は落ち着いていますが、世界の物流の変化を通じて、木材の輸入価格に影響しています。
これら二つの「波」は、日々の価格変動の主役であり、最も分かりやすい値動きの理由と言えるでしょう。
価格の大きな方向性を決める「潮」-数ヶ月前の住宅市場
波の動きとは別に、もっとゆっくりと、しかし確実に価格全体の水準を変えていくのが「潮」の満ち引きのような大きな流れです。実は、木材の輸入価格の大きな方向性を決めているのは、世界、特に日米の住宅市場の動きです。
輸入価格の動きを分析すると、日本や米国の住宅着工が増加トレンドに転じてから、およそ3ヶ月から6ヶ月ほどの時間差をおいて、日本の木材輸入価格が上昇する傾向が見られます。これは、住宅需要の変化を受けて、海外へ木材を注文し、日本に船で到着するまでに時間がかかるためです。つまり、数ヶ月前の新規住宅着工関連のニュースは、未来の木材価格の「潮」の流れを読むためのヒント、いわば先行指標となるのです。
現在、世界の住宅市場は国ごとに状況が異なります。米国では底堅さが見える一方、日本では弱含み、中国では不振が続いています。このまだら模様の状況が、数ヶ月後の木材価格が大きく上がることも、下がることもない、方向感の定まらない「潮」の流れを形作っています。
予測を困難にする「うねり」-過去のパターンが通用しない変化
ここまでの「波」と「潮」の分析は、あくまで過去のデータから見られるパターンに基づいています。しかし、時には、これまでの常識を覆すような、予測不能な大きな「うねり」が発生します。
その代表例が、米国の関税政策や経済制裁といった政治的な動きです。例えば、米国が木材関連製品に関税をかけると、これまで米国に木材を輸出していた国々が、行き場を失った木材を日本など他の市場に安く売ろうとするかもしれません。逆に、地政学的な緊張からロシア産木材の流通が滞れば、他の国の木材の需要が高まり、価格が上がるかもしれません。こうした「うねり」は、過去の統計データからの分析だけでは捉えることができません。だからこそ、私たちは既存の予測を鵜呑みにせず、常に世界で新たな「うねり」が起きているかに目を向ける必要があるのです。
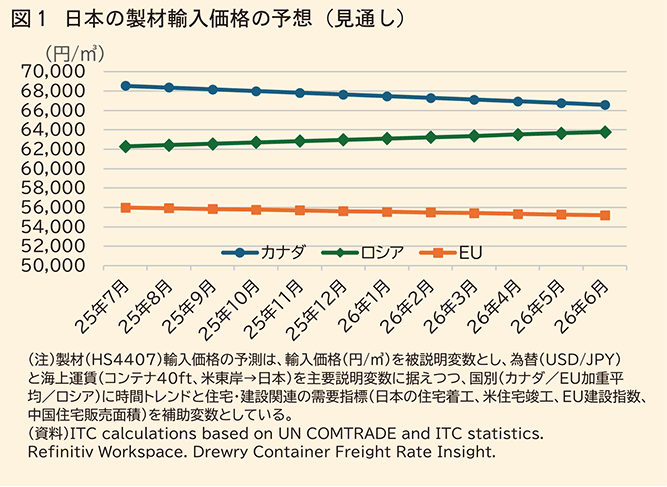
今後の価格を考えるヒント
では、これまでの「波」「潮」「うねり」という3つの視点を踏まえると、今後の木材価格はどうなるのでしょうか。世界の木材需要の現状を見てみましょう。米国では住宅ローン金利の低下を背景に売買契約が増加に転じ、「底入れの芽」が見え始めました。しかし、雇用の伸び悩みといった逆風もあり、力強い回復とまでは言えません。EUは建設生産が持ち直し、欧州材の価格を支えやすい環境です。一方で、日本は住宅着工の減少が、中国は住宅販売の低迷が続いており、住宅主導の大幅な押し上げは見込みにくい状況です。国や地域によって需要の「潮」は強弱まだら模様です。
カナダ産やEU産、ロシア産の日本への製材輸入価格について、為替レートや海上運賃が現在の水準で安定するという仮定を置いた場合、予想される価格トレンドは図1の通りです。カナダ産・EU産は、世界的な住宅需要がそれほど強くないため、緩やかに下落すると考えられます。ただし、供給サイドの「潮」として、産地で山火事が増加しており、価格の下支え要因として働くと見込まれます。なお、ロシア産については、経済制裁という大きな「うねり」の影響で通常の取引コストに様々な追加費用がかかりやすい状況です。そのため、他の地域の木材とは異なり、緩やかな上昇圧力がかかりやすい構造にあります。
しかし、これはあくまで短期的な「波」が穏やかである、という限定的な条件下での見方です。例えば、さらなる円安や中東情勢悪化による海上運賃上昇といった急な「波」が発生すれば、この見通しは大きく変わります。木材価格の先行きを考える上で大切なのは、専門的な分析結果よりも、その背景にある仕組みを理解することです。「為替レート」「海上運賃」、そして「数ヶ月前の住宅市場」。この3つのポイントに注目するだけでも、輸入価格の大きな流れは、ぐっと読みやすくなるはずです。
株式会社農林中金総合研究所
農林中央金庫100%出資のシンクタンクとして、農林水産業と食と地域に特化したリサーチ、アドバイザリー、コンサルティングを展開。多岐にわたる領域をカバーし、多様なステークホルダーに価値を提供している。