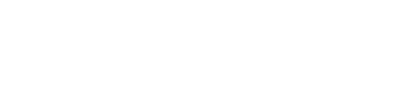ニュース&レポート
政府 南海トラフの地震活動の長期評価を公表 今後30年以内の発生確率は60~90%に
南海トラフ地震の発生確率が高まる
地震調査委員会は9月26日、南海トラフにおける大地震の発生確率を改訂しました。今後30年以内の発生確率について、これまで80%程度としていたところを、「60~90%」に見直されました。
同委員会はこれまで、南海トラフを含む海溝型地震について、震源域や規模、発生確率を長期評価として公表してきました。南海トラフについては、2013年にまとめられた第二版から10年以上が経過しており、新たな知見を踏まえて計算手法の不確実性が改善された上で、最新のデータを反映した改訂が行われました。
より一層の防災対策が必須に
今回の改訂では、今後30年以内における同地震発生確率の算出に当たり、二つの計算モデルで検証がなされました。過去における同地震の平均的な発生間隔のみを用いた「ブラウン緩和振動過程モデル(BPTモデル)」では発生確率が20~50%、発生間隔と地震ごとの隆起量を用いた「すべり量依存BPTモデル(SSD-BPTモデル)」では発生確率が60~90%程度以上となりました。
この計算結果に関する信頼性については、現在の科学的知見からは優劣をつけ難いとしています。しかし、海溝沿いで発生する地震の起こりやすさを分類する4段階のランクでは、ともに最も高い「Ⅲランク」に分類されることから、いずれも巨大地震の切迫性が非常に高い水準であることが示されました。
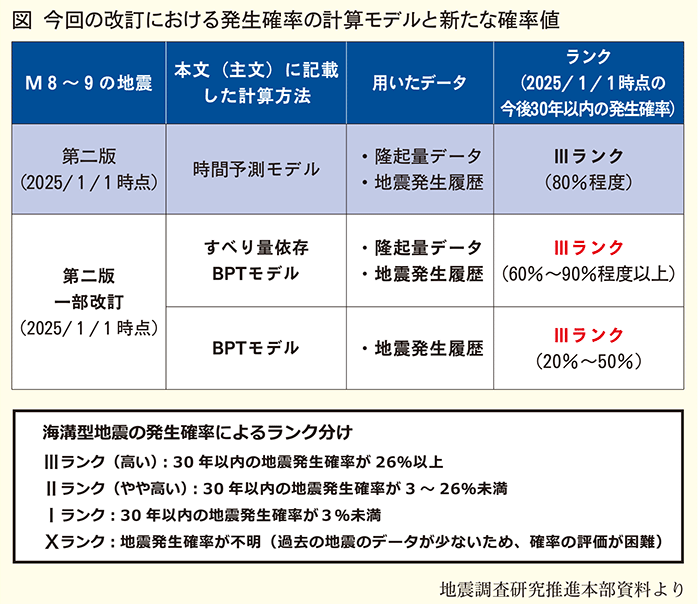
国、地方公共団体、住民等は、地震発生に対する防災対策や日頃からの備えに、引き続き努めていくことが求められるとしています。また、確率の具体的な値を示す必要がある際には、「疑わしいときは行動せよ」等の考え方に基づき、二つの計算方法のうち、より高い数値の「60~90%程度以上」を強調することが望ましいとしています。
長期評価における研究を推進
同委員会は、南海トラフの地震は震源域や発生間隔に多様性があることを踏まえ、今後は、多様性を説明する地震の発生モデルに基づき、長期評価を行う必要性を示しました。具体的には、歴史記録や津波堆積物などから過去地震の痕跡データを収集し、多様な地震の中に複数のタイプが存在する可能性について検証を推進していくとしています。また、海底の地殻変動を測定する技術の進展に伴い、既存観測点でのデータを継続的かつ長期的に蓄積するとともに、観測の時間密度を高めることも必要としています。