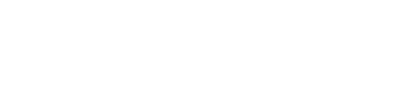ニュース&レポート
ナイスビジネスレポート編集部 拡大が見込まれるJAS構造材のニーズ
今年4月に施行された改正建築基準法により、小規模建築物でも構造計算が必要となる範囲が広がりました。これに伴い、品質や性能が明確に保証されたJAS材の需要が高まることが見込まれます。今回は、JAS材を採用するメリットに加え、基準の合理化を目的として行われた製材JASの改正内容について改めてご紹介します。
JAS材は認証工場でのみ生産可能
JAS(日本農林規格:Japanese Agricultural Standards)は、「日本農林規格等に関する法律」に基づき、農林水産大臣が農林水産物について、品質や成分、生産・管理方法などの基準を定めた国家規格です。生産・流通の効率化、消費者の合理的な選択といったメリットをもたらすものであり、木材では製材や集成材をはじめ、13の品目について規格が定められています。これらの規格は、それぞれ5年ごとに時勢にあったものに見直しが図られます。
JASマークを表示したJAS材は、JAS認証工場でのみ製造することが可能です。JAS認証工場は、それぞれの製造工程において厳格な品質管理基準を満たした上で製造し、最終製品で格付検査を行った後、JAS材として出荷されます。また、JAS認証を行う認証機関は、工場における製造工程や最終製品がJASの要求事項を満たしているか、厳格に審査した上で工場を認証します。認証を与えた後も、毎年定期的に監査を行い、JAS材の製造能力が維持されていることを確認しています。更に、農林水産大臣の指示を受けて、FAMIC((独)農林水産消費安全技術センター)が認証機関の検査を行います。こうして、JAS材の品質の確保には、何重にも厳しいチェックが実施されています(図1)。
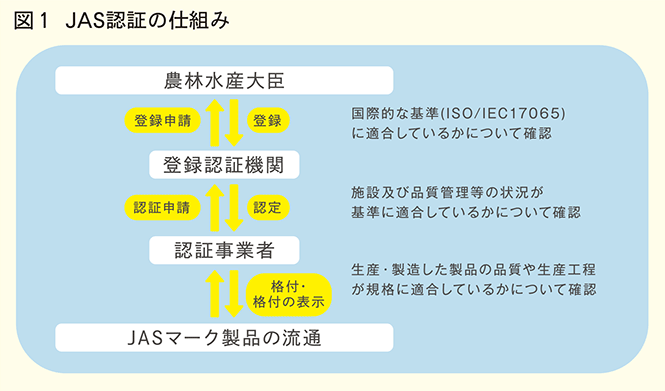
強度・寸法の高い安定性
JAS材を採用するメリットは多岐にわたります(図2)。木材はそのままでは強度等の性能にばらつきが生じますが、JAS材は品質・性能が明確であり、強度等級が材面に表示されます。JASの強度等級は、建築基準法関係告示において定められている基準強度と結びついており、構造計算において最適な木材の利用が可能です(図3)。また、材面等に表示してある寸法においても、その寸法や曲がりの許容範囲についてJASの基準が定められており、寸法の確実性も有しています。加えて、防腐・防蟻等木材の耐久性を向上させる保存処理が可能なほか、JAS材のうち接着剤を使用したものは「F☆☆☆☆」など、ホルムアルデヒド放散量を表示しており、屋内においてもシックハウス対策として使用できます。
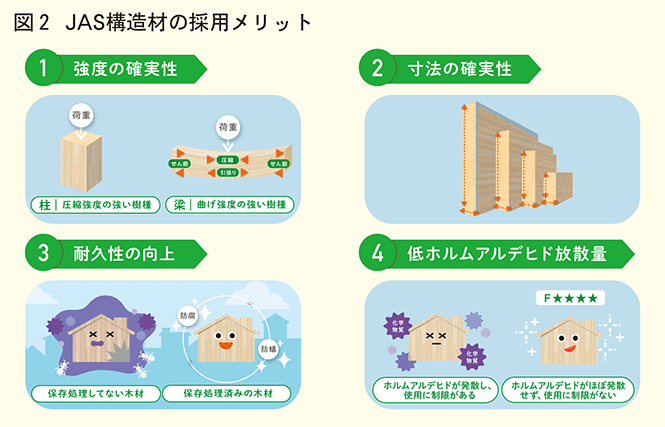
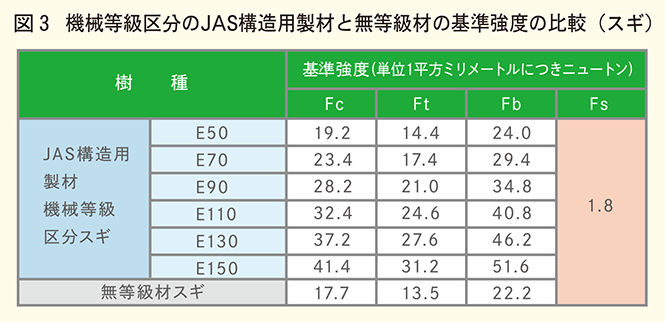
なお、JAS材は国産材でも製造されており、ウッドショック等の調達リスクの分散や、環境意識の高い施主へのPRとして、国産JAS材を活用することができます。また、木材のたわみ易さを表す「ヤング係数」が同じ場合、スギはベイマツに比べ、圧縮、引張、曲げの基準強度が大幅に高く設定されているほか、ヤング係数が低くても強度の低下は少ないため、構造材としての利用価値が高いと言えます。
構造計算範囲の拡大でJAS材ニーズが高まる可能性
2022年の主な林産物の供給量に占めるJAS製品の割合(格付率)は、CLTや集成材、合板等では、ホルムアルデヒド放散量の基準を満たすことを示す必要があるため、CLTが87%、集成材が83%、合板が67%と、格付が進んでいる状況です。一方、製材では11%、構造用製材に絞っても27%と低い水準となっています。これには、本推計時点では、2階建て以下かつ500㎡以下の小規模な木造建築物において、構造関係規定の審査が省略されていたことが要因と考えられます。
しかし、今年4月に施行された改正建築基準法により、建築確認・検査の審査省略制度の対象が見直されました(図4)。「2階建て以上または延べ面積200㎡超」の木造建築物等は「新2号建築物」に該当し、建築や大規模の修繕・模様替を行う場合、全ての地域で建築確認・検査が必要となりました。「新2号建築物」では、「構造関係規定」を含む建築基準法令の全ての規定が審査・検査の対象となるため、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質について仕様表に明記する必要があります。加えて、同改正によって、構造計算が必要となる範囲が拡大し、高さが16メートル以下の場合は、階数によらず延べ面積300㎡超の建築物で構造計算が必要となるほか、仕様規定における柱の小径基準も見直され、建築物の荷重の実態に応じた算定が求められるようになりました。JAS材は品質・性能を明確に示すことが可能なこと、無等級材に比べて高い強度で計算できること等から、スムーズな建築確認や合理的な設計を可能とする木材として、ニーズが高まることが想定されます。
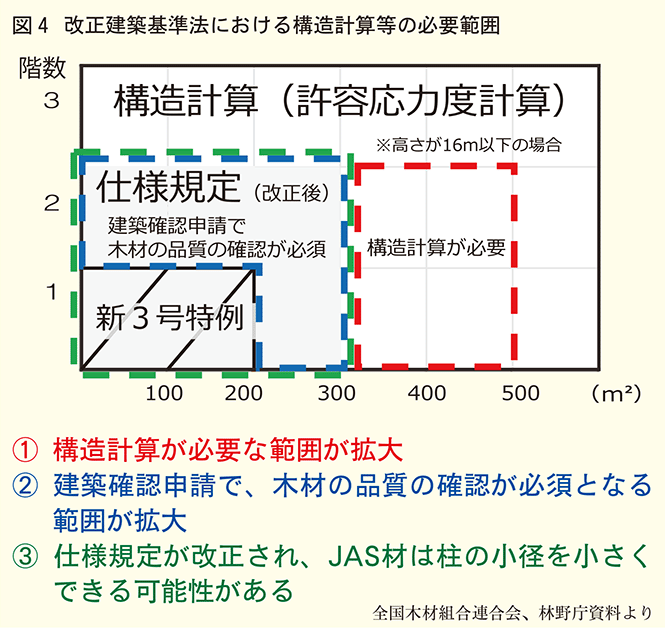
製材JASの利用拡大に向けた基準合理化が施行
こうした状況を受け、農林水産省は製材JASの見直しを実施、7月30日から改正内容が施行されました。本改正では主に、①曲げヤング係数(強度)の基準の変更、②目視等級区分の検査方法の追加、③寸法許容差の合理化が実施されました。
①曲げヤング係数(強度)の基準の変更については、これまでの上限値と下限値による管理から、平均値と下限値による管理に見直されました。これにより、検査のサンプルに強度の高い製材が含まれていた場合、従来では上限を超えた製材は不適合となっていたものも、格付けが可能となりました(図5)。②目視等級区分の検査方法の追加では、構造用製材における節や丸身といった材面の欠点の測定方法に、目視に加えて「カメラ撮影」「レーザー照射等」が追加され、より精度の高い測定ができるようになりました。③寸法許容差の合理化については、含水率20%以下の構造用製材について、木口の寸法許容差の下限が「-0㎜」から「-0.1㎜」に見直され、自然乾燥による収縮が生じた場合でも、格付けが可能となりました。
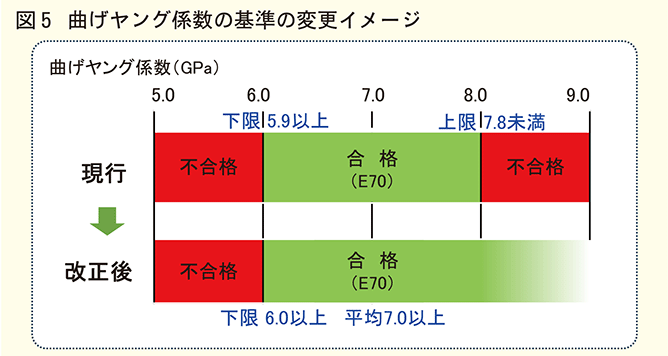
本改正に加えて、製材工場の負担を軽減するため、格付け時の試験片作成のコスト削減につながる「非破壊検査」や、単独でのJAS認証に向けた体制管理が困難な中小工場が連携して認証を取得する仕組みの導入も検討されています。今後も、JAS材の利用拡大に向けた動きが推進されることが見込まれます。
木材事業者のためのプラットフォーム「もりんく」
JAS材の調達や製材事業者の選定には、全国木材組合連合会が運営する木材製品情報サイト「もりんく」を活用することができます。「もりんく」は、川上から川中・川下まで、木材の生産・流通・加工・販売に携わる事業者のための情報プラットフォームです。同サイトでは、製材事業者が各工場で生産するJAS材を含む木材製品の供給情報を登録することができます。これにより、設計者・施工者は、JAS材などの木材製品の供給情報を検索・閲覧し、各製品の生産状況、在庫量、納期等を問い合わせることができます。製材事業者にとっては、供給しやすい製品の周知や発注見込みの情報の早期入手、設計者・施工者にとっては、調達しやすい木材の把握による設計の手戻りや調達コストの削減につながるといったメリットがあります。
サイト内の「JAS認証工場詳細検索」では、全国のJAS認証工場を、地域やJAS認証区分で絞り込んで検索することが可能です(図6)。表示された工場の認証情報など詳細の情報も確認することもでき、近隣エリアでJAS材の調達が可能な工場を容易に把握できます。
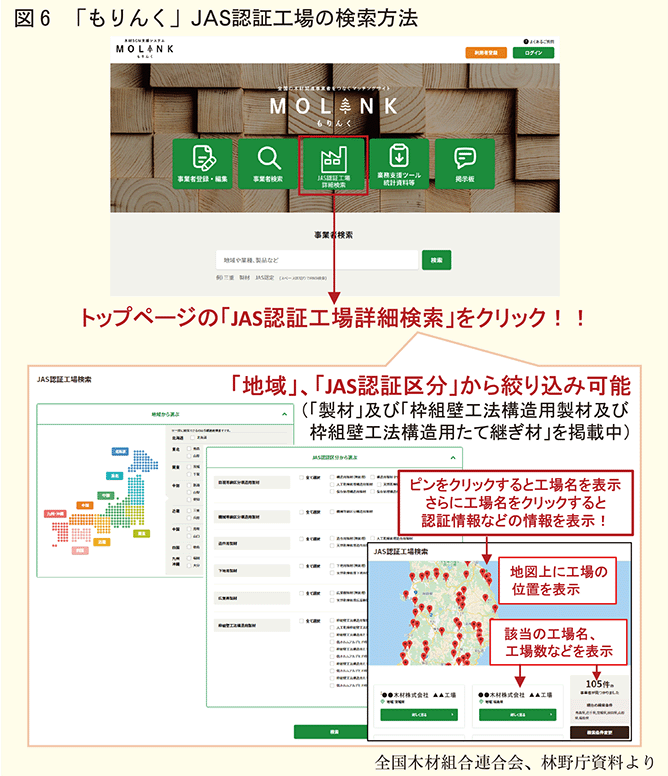
ナイスグループ JAS材の生産機能

ウッドファースト㈱では、大径材にも対応するツイン帯鋸無人製材機、高速多軸ギャングモルダーなど最新鋭の製材加工機械(機械等級JAS認定取得・徳島県内初)により、多様化するお客様のニーズに即した高品質な製品の生産に取り組んでいます。
土台・梁・桁・柱といった建築用部材を中心に生産しており、取り扱う樹種はスギが約8割、ヒノキが約2割となっています。原材料となる丸太については、安定した供給源の確保に加え、ナイスグループの社有林である「ナイス徳島の森」から伐採した丸太も利用して、国産材の需要拡大を推進しています。

㈱かつら木材商店は、紀州材を中心に国産ヒノキを専門として製材事業を手掛けており、主に一般住宅、公共施設等に使用する建築用材を建築会社、工務店、ビルダー、ハウスメーカー、木材問屋へ提供しています。年間約38,000㎥の原木を消費し、紀州材のトップメーカーとして関西圏及び中部圏を中心に全国へ販売しています。また、グループ会社の㈲きのくに林産加工は、主にプレカット加工事業を手掛け、在来軸組工法や金物工法に対応するなど、その加工実績は年間約36,000坪となっています。