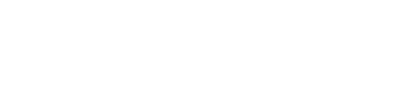ニュース&レポート
防災の日特集 発生が予測される大規模地震 早期対策で被害を最小限に
9月1日は、様々な災害についての認識を深めるとともに、防災対策の重要性を改めて考える「防災の日」と定められています。今回は、南海トラフ巨大地震をはじめ、近年発生する可能性が高いとされる大規模地震に関する、内閣府が公表している被害想定や特徴、対策の方向性等をまとめました。
南海トラフ地震 全国の約3割、人口の約5割が被災する恐れ
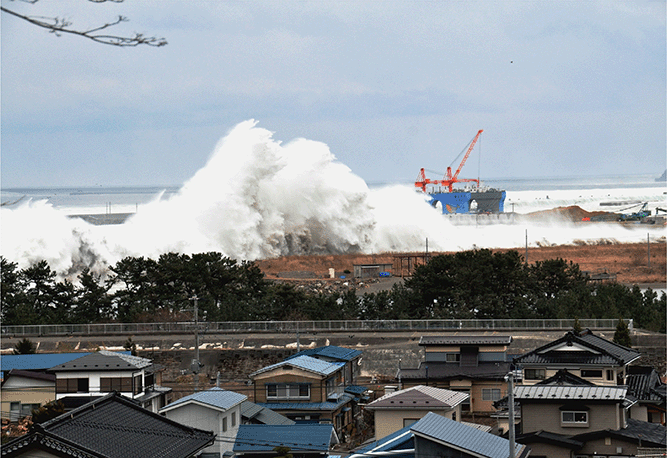
南海トラフ沿いの大規模地震は、歴史的に繰り返し発生し、その度に甚大な被害をもたらしてきました。政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、今後30年以内にマグニチュード8~9程度の地震が発生する確率は80%程度とされています。
南海トラフ巨大地震では、強い揺れと短時間で到達する巨大な津波が広範囲に襲来し、中京都市圏や京阪神都市圏をはじめとする人口・社会経済活動集中地域から離島・半島、中山間地まで、極めて甚大な被害が多様な形態で発生すると想定されています。被害想定は、死者数が最大29.8万人、全壊焼失棟数は最大で約235万棟と推計されており、政府は今後10年間の減災目標として、死者数を約8割、全壊焼失棟数を約5割減らすことを掲げています。
南海トラフ巨大地震の特徴として、震源域が非常に広いため、強い揺れと巨大津波が広範囲に同時に発生する点が挙げられます。被災市町村は31都府県の764市町村に及び、その面積は全国の約3割、人口は全国の約5割を占めます。また、想定震源域の東側と西側でマグニチュード8クラスの地震が時間差で発生する「半割れケース」も想定されており、後発地震への備えにより、被害は大きく変化することが見込まれます。
対策においては、超広域かつ甚大な被害が発生する中で、人的・物的リソース不足等の困難な状況が想定され、行政による対応だけでは限界として、「行政が守る者、国民が守られる者」から「行政・地域・事業者・国民がともに災害に立ち向かう」という考え方への転換が不可欠とされています。具体的に実施すべき内容としては、津波避難意識等の向上に向けたリスクコミュニケーション及び防災教育の充実や、補助制度・税制優遇措置等の周知等による住宅・建築物の耐震診断・耐震改修等の促進、木造住宅密集地域等の火災危険性が高い地域における感震ブレーカーの普及などが挙げられます。
「南海トラフ地震臨時情報」のガイドラインを改訂
時間差をおいて発生する地震等への対応の強化としては、気象庁から発表される「南海トラフ地震臨時情報」の実効性を高めることが求められます。こうした中、内閣府は8月7日に「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」の改訂版を公表しました。昨年8月に「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が運用開始後初めて発表された際の各地の対応・反応を受け、巨大地震注意に関する記載の充実等が図られています。臨時情報の基本的な考え方として、行政や事業者等は「地域や利用者等の安全確保」と「社会経済活動の継続」のバランスを考慮しつつ、自らの行動を自ら判断することの重要性に言及したほか、鉄道は原則運行規制はしない旨等が盛り込まれました。
首都直下地震 地震火災の同時多発・延焼リスクが課題

首都直下地震は、我が国の政治、行政、経済の中枢を担う機関が高度に集積する東京圏を直撃する可能性のある地震です。マグニチュード7クラスの都区部直下地震を想定した場合、揺れによる全壊家屋は最大約17.5万棟、建物倒壊による死者は最大約1.1万人と推計されています。更に、地震火災による焼失は最大約41.2万棟(倒壊等と合わせ最大約61万棟)、火災による死者は最大約1.6万人(建物倒壊等と合わせ最大約2.3万人)に上る可能性があります。ライフラインの被害も甚大で、電力供給能力が5割程度に低下することで広域で停電が発生し、上下水道の約5割の利用者で断水、通信は音声通話の9割が規制されるなど、深刻な影響が想定されます。交通面では、都区部の一般道は瓦礫により閉塞、復旧に1カ月以上を要する見込みです。
首都直下型地震の特徴として、大都市特有の巨大過密が災害時の脆弱性を高める点があります。都心部を囲むように分布する木造住宅密集市街地では、火災の同時多発・延焼リスクが非常に高いほか、海抜ゼロメートル地帯も広く分布し、浸水被害の長期化が懸念されます。更に、交通インフラの被災や大量の帰宅困難者の発生により、深刻な道路交通麻痺の発生が見込まれ、救命・救助活動や復旧作業に著しい支障が生じる可能性があります。また、瓦礫処理や仮設住宅設置のための空間・用地の不足も課題となります。
発災時の対応への備えについては、発災直後からの時間経過に沿って整理されています。発災直後の対応(概ね10時間)としては、「国の存亡に係る初動」とし、被害状況に応じて「災害緊急事態の布告」を迅速に発し、一般車両の利用制限、道路啓開等における放置自動車及び瓦礫撤去の措置、応急対策要員の確保、民間への協力要請等、現行制度の速やかな実施を図るとしています。発災からの初期対応(概ね100時間)としては、「命を救う」ために発災地域内の人員でできることを最大限実施する備えが必要とし、救命救助活動や災害時医療の体制強化等が求められます。初期対応以降としては、被災者の生活の確保、経済活動の再開が目指されるとし、被災者・災害時要配慮者への対応や、避難所不足等の対策を検討すべきとしています。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 積雪や寒さによる逃げ遅れ、低体温症の恐れ

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震は、北海道から東北地方を中心に、東日本大震災を超える甚大な人的・物的被害が想定されている地震です。
被害想定では、死者数が日本海溝モデルで最大約19.9万人、千島海溝モデルで最大約10万人と想定されています。建物被害は、全壊棟数が日本海溝モデルで約22万棟、千島海溝で約8.4万棟に達し、全壊棟数の大半は津波によるものです。想定される津波の高さは、青森県以北や岩手県内では25メートル以上と推定され、東日本大震災が発生した津波より高くなる地点があるとしています。
また、被災地が積雪寒冷地であることが原因となる被害も想定されます。冬季では積雪荷重により建物倒壊による死者が増大するほか、津波からの避難速度低下により死者数が増大する可能性があります。津波から難を逃れても、屋外や寒い屋内での長時間滞留により低体温症要対処者が約4.2万人に達するという推計もあります。
対策としては、これまでの地震・津波対策の延長線上の対策では十分な対応が困難とし、積雪寒冷地特有の課題や、広大な土地、都市間距離の大きさ等の北海道・東北地方の沿岸地の特性を踏まえた対策を講じることが必要としています。その上で、津波からの人命の確保に向けては、避難距離や避難時間の短縮を目指した津波避難ビルの指定、津波避難タワーやシェルター付き避難路等の設置に加え、人口が少ない平野部地域での自動車を用いた避難の検討が求められています。また、冬季の低体温症のリスクを踏まえ、避難所における防寒機能を備えた空間の確保や二次避難の経路確保といった避難時における防寒対策等も必要としています。加えて、防寒対策・救助活動に電力が必要なことから、ライフライン・インフラの確保対策において、積雪寒冷地では電力の広域的な機能確保が特に重要であり、ライフライン施設の耐震化や電力復旧の優先順位付け、早期の復旧見通しの公表に取り組むべきとしています。
>国土交通省における南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策
国土交通省 耐震化の推進に向けて特設サイトを開設
国土交通省は8月1日、住宅の耐震化の進め方などの情報を提供する特設サイト「家族を思う、強い家」を開設しました。大地震から命や財産を守るためには、住宅や建築物の耐震化について所有者が自らの問題と認識して取り組んでいくことが重要とした上で、改修を実施した住まい手へのインタビュー記事や、住宅の耐震性に関するセルフチェック「誰でもできるわが家の耐震診断」、地方公共団体による補助金・支援制度等が掲載されています。また、「耐震改修の専門家の選び方」についても解説され、耐震診断から設計、工事における建築士や工務店の役割について述べられているほか、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が紹介されています。