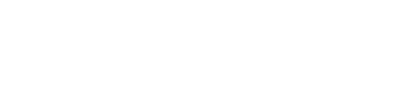ニュース&レポート
国土交通省 「住宅分野における建設技能者の持続的確保懇談会」 担い手確保に向けた施策の方向性を整理
住宅の性能向上で担い手の役割も増加
国土交通省は8月6日、「住宅分野における建設技能者の持続的確保懇談会」の第4回を開催し、これまでの議論を踏まえたとりまとめの骨子案が公表されました。近年、住まいに求められる性能が上がり、住宅の供給・維持管理に携わる大工等の担い手の役割も増えている一方で、担い手の高齢化等から、今後、住宅の安定供給等が困難となることが懸念されています。本会議では、質の高い住まいの安定供給や適切な維持管理が行われる社会の実現に向け、住宅建設技能者の確保における課題について議論が行われてきました。
今回公表されたとりまとめの骨子案では、住宅分野における建設技能者等の現況や今後の見通しが整理された上で、取り組むべき課題や施策の方向性が示されました。
新規入職者の増加と離職率の低下の両軸で対策
住宅分野における建設技能者等の現況として、木造住宅の担い手である大工就業者数は、2020年に約30万人と20年間で半減しており、人数の減少率と60歳以上の比率は建設業従業者全体に比べて大きくなっていると指摘しています(図)。将来推計では、2035年には大工就業者数が約15万人と、2020年から約半減することや、2030年以降の建設技能者全体のうち50代以上が6割となる一方、大工は約7割以上になることが示され、今後も大工の年齢層は建設技能者全体と比べても高い傾向が続く可能性があるとしています。
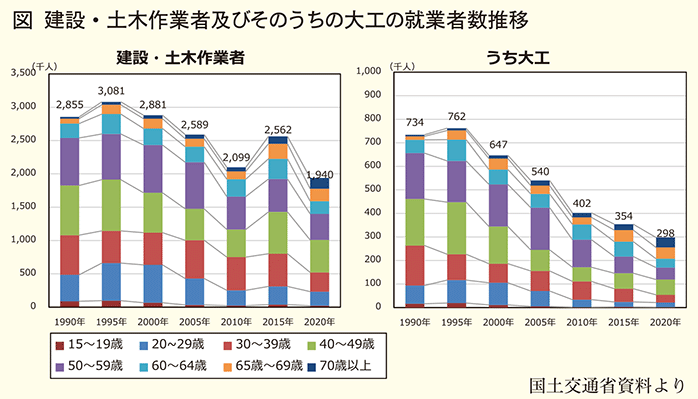
こうした状況を踏まえ、住まい供給の担い手である住宅分野の建設技能者の確保に向けて、住宅分野の建設技能者になる入口の「入職者の増加」、技能者の定着を進め、離職率を減らすための「職場環境や将来見通しの整備」に加えて、これらを行った上でなお担い手が不足することを見据えた「住宅建設の省力化・効率化」の三つに取り組むべきという方向性が示されました。
「入職者の増加」については、新規入職者の確保推進に向け、若年層に向けた住教育の一層の推進によるモノづくりの魅力発信や、工務店による実技指導を含めた建設業界と教育機関の連携強化を挙げています。また、女性の入職促進として、住宅版快適トイレの普及等による働きやすい住宅生産現場の実現や、体格差等を懸念せずに作業できる工程の明確化が挙げられました。「職場環境や将来の見通しの整備」については、地域工務店の経営基盤強化に向けた複数工務店による協力業者会の運営・職方の共有・共通化及びバーチャルカンパニー化や、社員大工化の促進、CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録促進等が挙げられています。「住宅建設の省力化・効率化」については、DXツールやAIの活用による事務支援・現場作業の効率化や、川上から川下までの業界全体のフローの最適化を挙げています。
中長期ビジョンの策定も見据える
同省は引き続き本会議において議論を進め、11月頃の住生活基本計画の中間とりまとめへの反映を目指すとしています。加えて、本会議でとりまとめた課題を踏まえ、目指すべき将来像や取り組みの方向性を整理した「住宅建設技能者の持続的確保に向けた中長期ビジョン(仮称)」の策定が必要としています。