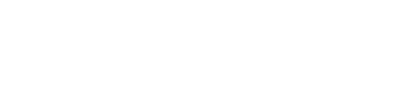ニュース&レポート
厚生労働省 改正労働安全衛生規則を施行 事業者に対して熱中症対策を義務化
厚生労働省は6月1日に改正労働安全衛生規則を施行し、事業者に対して職場における熱中症対策を講ずることを新たに義務付けました。今回は、熱中症対策の強化に向けた取り組みや、早期に求められる対策などをご紹介します。
建設業における死亡割合は全体の3分の1に
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分のバランスが崩れるほか、循環調整や体温調整等の重要な調整機能が破綻することなどで発症する障がいの総称です。症状は、他覚症状として失神や大量の発汗、痙攣が出現し、自覚症状としては、めまいや吐き気、高体温等、様々な身体の変化が現れます。近年の気候変動による夏季の気温上昇等で熱中症による業務上疾病者数は高止まりの傾向が続いており、一層の対策の推進が求められています。
2024年における職場での熱中症による死傷者数は1,257人となり、統計を取り始めた2005年以降最多となりました。業種別の発生状況を見ると、製造業が235人、建設業が228人の順で多く発生しています。このうち死亡者数は31人となり、建設業が10名と全体の3分の1を占めました。また、2020年以降の5年間に発生した熱中症による死傷者数を業種別で見た場合も死傷者・死亡者ともに建設業と製造業で多く発生しており、高水準での推移が続いています(図1)。死亡災害の事例としては、WBGT(暑さ指数)の確認ができなかったことや、発症時・緊急時における措置の確認及び周知ができていなかったこと等が挙げられます。
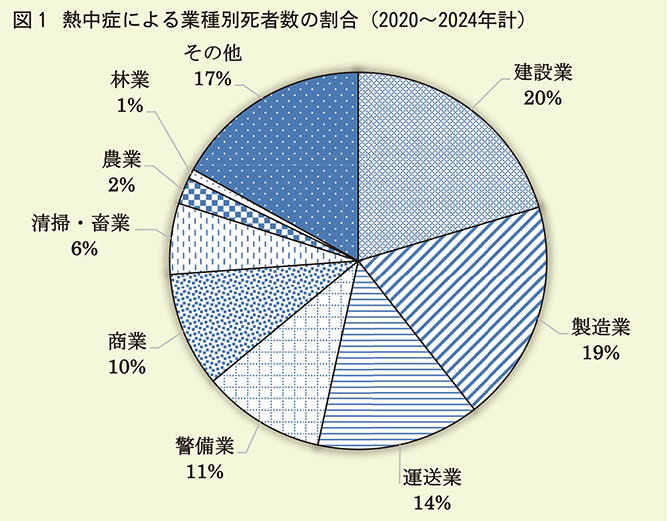
WBGTを活用した熱中症対策を呼び掛け
こうした中、6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策の強化が図られています。職場での熱中症による死亡災害は「初期症状の放置、対応の遅れ」が多いことから、熱中症のおそれがある労働者を早期発見して重篤化を防止するため、事業者に対して「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。具体的には、「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知が必要となります。また、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、①事業所における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等、②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係者への周知が求められます。
義務の対象は、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて作業することが見込まれる事業者となります。WBGTとは暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、熱中症予防のための情報・資料サイト等で確認が可能となります。身体作業強度とWBGT基準値を比較することで熱中症を予防し、基準値を超える場合には、作業場所における基準値の低減や身体作業強度の低い作業へ変更することが求められます(図2)。やむを得ず基準値を超えてしまう場合には、熱中症予防対策を講ずる必要があり、具体的には、日陰や冷房を備えた涼しい休憩場所等を設置する「作業環境管理」、作業時間の短縮や作業中の巡視等を行う「作業管理」、日常の健康管理や労働者の健康状態の確認を行う「健康管理」、熱中症の症状や予防方法等に関する「労働衛生教育」の実施となります。
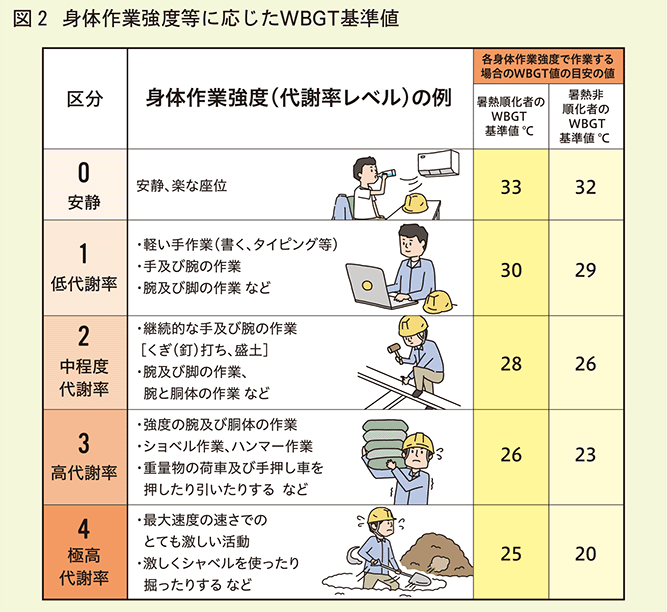
速やかな初期対応で重篤化リスクの予防を
熱中症のおそれのある者を発見した場合は、速やかに作業の離脱や身体の冷却を行い、「意識の有無」だけで判断せず、「返事がおかしい」「ぼーっとしている」など、普段と様子が異なる場合も異常等ありとして救急隊を要請することが推奨されています(図3)。また、医療機関までの搬送の間や経過観察中は一人にせず、単独作業の場合は常に連絡できる状態を維持することが求められます。なお、回復後にも体調急変などにより症状が悪化するケースもあるため、連絡体制や体調急変等の対応をあらかじめ定めておくことも呼び掛けています。
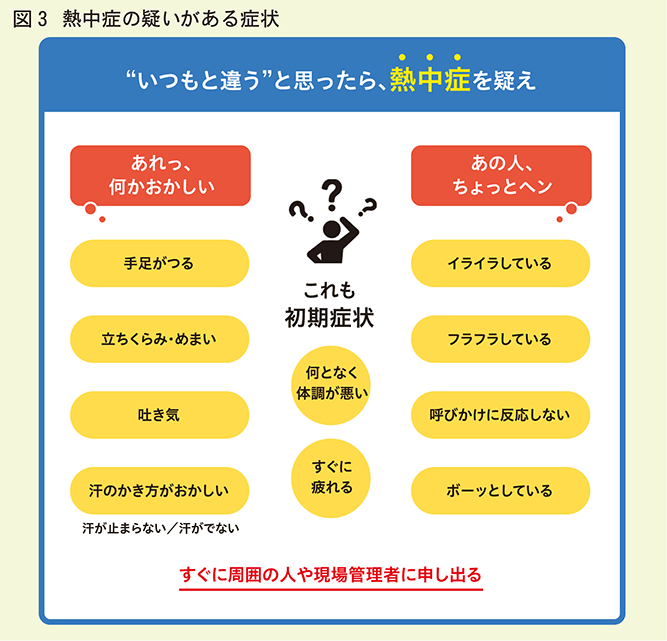
熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となるほか、死亡者の約7割は屋外作業となっていること等から、建設現場における熱中症予防対策は極めて重要となります。同対策の詳細は熱中症予防サイトより確認が可能となります。