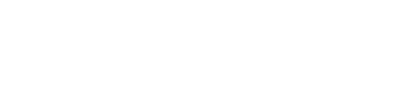ニュース&レポート
内閣府 「令和7年度 年次経済財政報告」を公表 住宅投資の動向や今後の課題を整理
3月の着工戸数は法改正前の駆け込みで急増
内閣府は7月29日、「令和7年度年次経済財政報告」を公表しました。本報告では、日本経済の現状と課題の分析を通じて、今後必要となる政策の検討に資するための議論がなされており、民間部門における最終需要の一つである住宅投資の動向についてまとめられています。
新設住宅着工戸数は、足元ではおおむね横ばいで推移していましたが、2025年3月には前月比35%増と急増しました。この背景には、同年4月に施行された改正建築物省エネ法及び建築基準法を見据え、貸家、持家、分譲戸建における駆け込みの着工が発生したことが主な要因としています。形態別に見ると、持家や分譲戸建てといった一戸建住宅は、長期的に緩やかな減少傾向にあります。要因としては、持家のニーズが相対的に小さい単身世帯の増加、ニーズが大きい夫婦とこども世帯の減少といった世帯構成の変化や、建築コストの上昇及び高止まりが挙げられています。マンション等の共同分譲住宅についても同様に、建築費の上昇や大規模な土地取得の難しさが影響し、緩やかな減少傾向にあります。貸家については、法人による建設は堅調に推移する一方で、個人による建設は低調となっており、建築費の高止まりや調達金利の上昇により、賃貸利回りの上昇が限定的であることなどが背景にあるとしています。
中古住宅取引が住宅投資の4分の1を占める
中古住宅については、リフォーム工事が住宅投資の1割強、仲介手数料が1割台半ばを占め、合わせて住宅投資の4分の1を占めています。価格の優位性から中古住宅の販売は戸建て・マンションともに増加傾向にあるほか、住宅リフォームの受注高も、省エネリフォームへの各種補助金効果によって底堅く推移しています(図1・2)。ただし、リフォーム受注額は人件費を含む工事費の上昇により、名目ベースでは増加している一方、価格変動を除いた実質ベースでは横ばいから緩やかな減少傾向となっています。
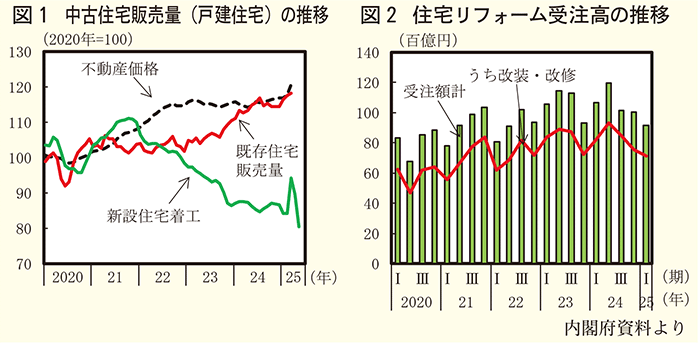
人口・世帯構造の変化に伴い、住宅ストック戸数は世帯数を上回る状況が続いていることから、中古住宅取引市場の活性化を進めることで、豊かなストックを有効活用することが一層重要としています。
住宅ローン金利上昇の影響も分析
本報告では更に、昨今の住宅ローン金利上昇が家計に与える影響についても分析しています。2023年度時点では、新規貸出の8割超、既往貸付の7割が変動型となっています。総務省の「家計調査」によると、二人以上の世帯のうち2割強を占める住宅ローン保有世帯では、預貯金等の金融資産を住宅ローン等の負債が上回っており、変動金利の上昇が家計の負担増となり得るとしています。また、可処分所得に占める住宅ローン返済の負担率を世帯主の年齢別に見ると、平均で15.3%に対し、20代で22.0%、30代で16.4%と、若年層ほど返済負担が重い傾向が見られます。
変動金利型住宅ローンには、金利が変動しても5年間は返済額が変わらない「5年ルール」などの仕組みがあり、金利上昇が直ちに返済額に反映されるわけではありません。しかし、物価上昇が賃金の伸びを上回る状況が続けば、消費者マインドの下振れと相まって、住宅購入や消費支出を下押しする可能性があり、十分留意が必要としています。