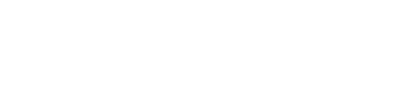ニュース&レポート
国土交通省 「住宅税制のEBPMに関する有識者会議」中間とりまとめ 住宅税制による住宅購入促進効果が顕著に
国土交通省は6月16日、「住宅税制のEBPMに関する有識者会議」の中間とりまとめを公表しました。同会議では、EBPM(Evidence Based Policy Making)の観点より、住宅ローン減税等主要な住宅税制の効果検証を進めています。今回は、その検証結果を税制別にご紹介します。
住宅税制による一定の効果を発揮
「住宅税制のEBPMに関する有識者会議」は、第208回国会における税法改正附帯決議等において、住宅ローン減税等の効果検証やEBPMの徹底等が求められていることを踏まえ、主要な住宅税制についての効果検証を行いました。今回の中間とりまとめでは、「住宅ローン減税」「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」「リフォーム促進税制」「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」の効果に関する検証結果が公表され、いずれの措置についても一定の効果が出ているとの見解が示されました。
省エネ性能の高い住宅の取得を促進
「住宅ローン減税」は、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除するものです。同制度の適用件数を見ると2023年度は42万6,097件となり、新築住宅購入者の約7割が活用しています。住宅購入に当たり住宅ローン減税の適用を「受けている(受ける予定)」と回答された方のうち、住宅取得数の約9万戸に相当する約21%が住宅ローン減税がなかった場合は住宅を「購入しなかった」と回答しており、住宅取得促進への効果が見られました(図1)。また、省エネ性能等の高い住宅及び子育て世帯への借入限度額の上乗せ措置についても、政策目的に対して一定の効果が発現しているとされました。子育て世帯への上乗せ措置がなかった場合、住宅の価格や住宅性能を下げていたとの回答結果が得られたほか、住宅性能については注文住宅、分譲住宅ともにZEH水準の住宅取得が促進された可能性が示唆されました。
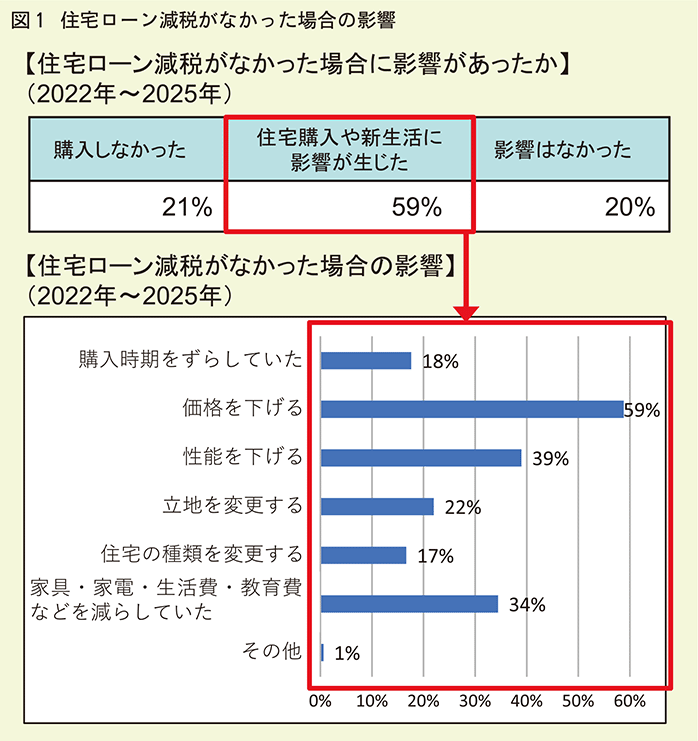
住宅取得時の初期負担軽減に寄与
「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」は、住宅取得者の初期負担の軽減を通じて居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税を一定期間減額するものです。2023年度における新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用件数は212件、認定長期優良住宅に係る固定資産税の減税措置の適用状況は56件となりました。同制度がなかった場合、「新築住宅を購入した」と回答された方のうち約16%が住宅を「購入しなかった」と回答したほか、長期優良住宅を購入した方の約26%が、上乗せ措置がなければ長期優良住宅ではない住宅を購入したと回答しています。所得階層別に見ても、中間層を中心に幅広い層に効果が生じていたとしています(図2)。
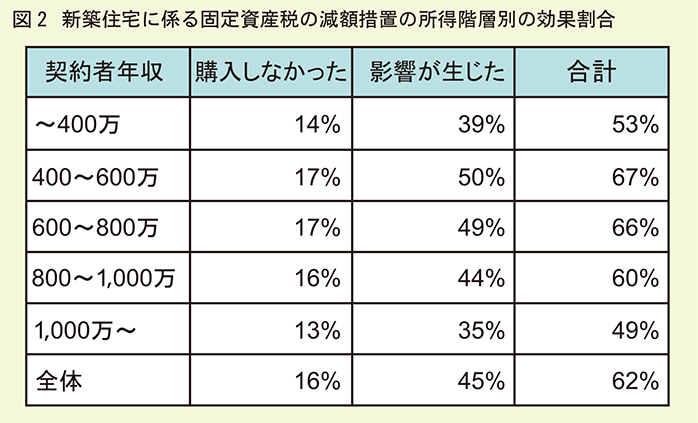
「リフォーム促進税制」は、既存住宅の一定の性能向上リフォームを行った場合、当該リフォームに係る対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%を工事年分の所得税額から控除する制度です。2024年度における適用件数は、耐震が最も高く2,876件となったほか、次いで省エネが1,782件、子育て対応が1,563件となりました(図3)。同税制は住宅性能向上に向けたリフォームの実施に影響を与えているほか、リフォーム実施者の負担軽減を通じた良質な住宅のストックの形成にも一定の効果が見られるとの見解が示されました。
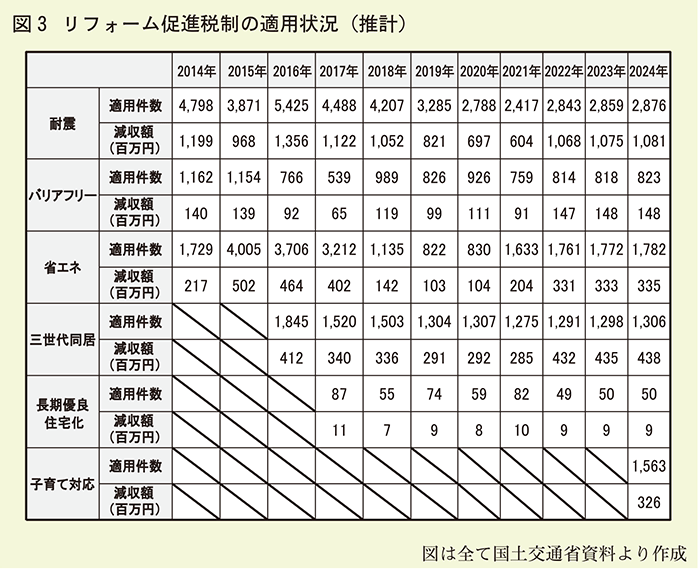
そのほか、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年内に、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡に当たり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。2023度の適用件数は8,820件となり、想定される効果として、相続空き家及びその敷地の売り出し促進、更にはそれによる相続空き家の減少や増加の抑制等が示唆されました。
継続的な住宅税制措置を検討
今回の効果検証については、他の主要な住宅税制も含めて今後も継続的に実施すべきとしています。また、継続的に税制特例の対象となる消費者の多様な行動変容を把握するとともに、より精度の高い効果検証が実施できるようデータの充実に努める方針です。