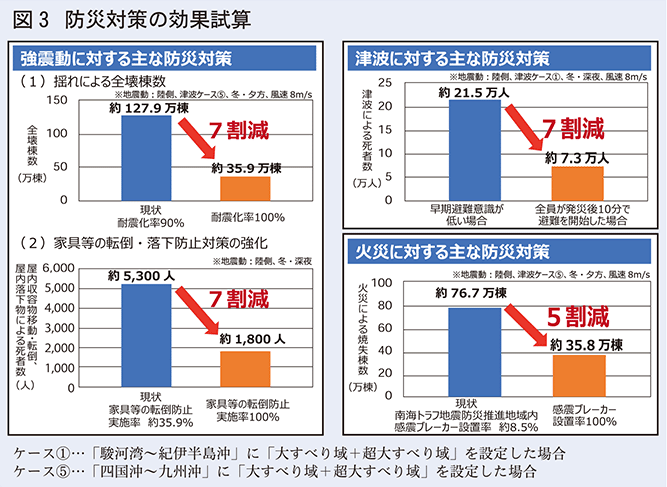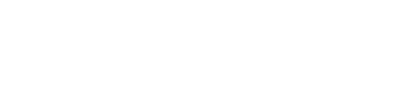ニュース&レポート
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 最大クラス地震の被害想定を公表 防災対策を講じた場合の被害は7割減に
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは3月31日、南海トラフ巨大地震における最大クラス地震の被害想定などについてまとめた報告書を公表しました。今回は、想定される被害内容や、今後求められる災害対策等について紹介します。
各地において甚大な被害を想定
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは、中央防災会議において2014年に閣議決定した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(以下、基本計画)の策定から10年が経過することから、基本計画の見直しに向けた防災対策の進捗状況の確認や新たな防災対策の検討を目的に、防災対策実行会議の下に設置されました。
このたび公表された報告書では、強い揺れや津波が広域で発生することから、最大の死者数が約29.8万人、全壊焼失棟数が約235万棟を想定しているほか、経済被害は約292兆円との見込みを示しています(図1)。
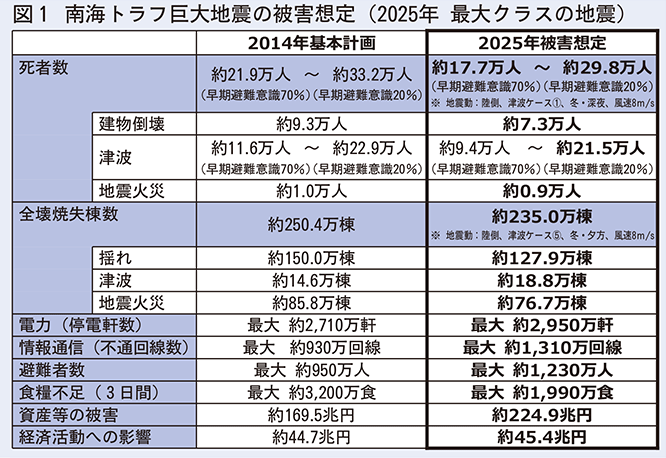
時間差で発生する被害への備えが重要に
南海トラフにおける地震では、マグニチュード8クラスの地震が時間差で発生する「半割れ」が想定されており、今回の報告書では、「南海トラフ地震臨時情報」等による後発地震への注意等、その特徴を踏まえた被害想定が算出されています。
後発地震が発生した場合、地震の揺れや津波高は、最大クラスの地震の揺れや津波高を超えることはないものの、震度6以上の揺れや浸水深1m以上の浸水に、続けて2回さらされる地域も存在すると想定しています。後発地震による新たな被害を軽減するためには、南海トラフ地震臨時情報や後発地震発生までの時間を最大限活用し、適切な対策・対応をとることが求められます(図2)。
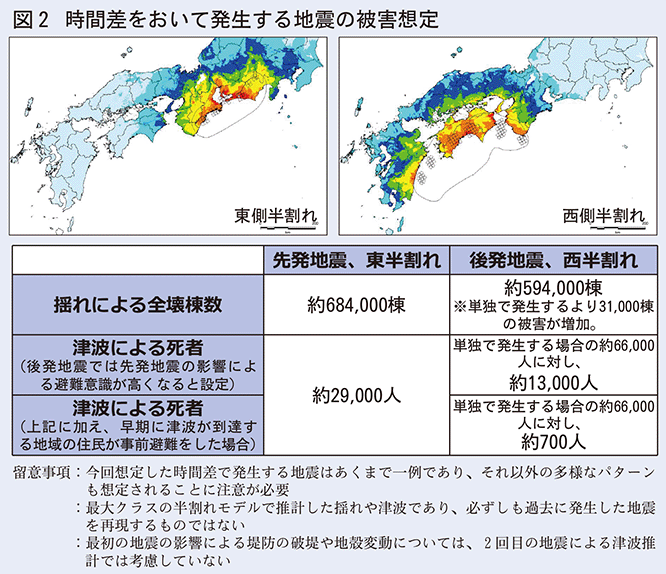
また、同巨大地震では各地域の特性によって異なる被害や影響が発生すると想定されています。例えば、大都市の中心市街地では、避難生活や災害医療に関連するリソースが不足するほか多数の企業が被災することで日本経済全体が停滞すると想定されています。また、沿岸部の工業地帯では、工場や港湾が被災し、サプライチェーンの寸断や地域経済の停滞が見込まれるほか、ライフライン供給に関わる施設が被災することで、ライフラインが長期にわたって停止すると予測されています。そのほか、中山間地域や半島・離島では、被災者支援が困難な状況となる地域・集落の発生が、海抜ゼロメートル地帯では、広範囲にわたる浸水によって多数の人的被害や避難者等が発生すると想定されています。
住宅の耐震化率は9割超に
主な防災対策の進捗状況についても公表されており、全国の住宅の耐震化率を見ると、2008年は約79%にとどまっていたところ、2023年は約90%となりました。また、同じく全国の災害拠点病院等の耐震化率が、2017年の約89%から2022年には約95%まで伸長したほか、企業のBCP策定率などについても向上するなど、近年における同巨大地震に対する対策は一定程度の進展が見られるとしています。
一方、社会状況は大きく変化しており、防災対策の進捗や社会状況の変化、過去の自然災害から得られた教訓を踏まえて、検討を実施するなどとしています。10年間の主な社会状況の変化として、人口動態を見ると人口減少・高齢化の進展や単身世帯の増加が続いていることから要配慮者・要支援者の増加や被災地の孤立化等が懸念されています。一方で、技術革新では、精度の高い状況分析や将来の予測が可能となることや、データ消失からの保護、応急対策の効率化等が期待されています。
防災対策の推進による被害軽減を推測
超広域かつ甚大な被害が発生する中で、人的・物的リソース不足等の困難な状況が想定され、あらゆる主体が総力をもって災害対策を講ずることが重要としています。このうち、被害の絶対量低減等のための強靱化・耐震化、早期復旧の推進に向けた取り組みとして、補助制度、税制優遇措置等の周知等による住宅・建築物の耐震診断、耐震改修等の促進のほか、木造住宅密集地域等の火災危険性が高い地域における感電ブレーカーの普及が求められます。加えて、社会全体における防災意識の醸成については、津波避難意識等の向上に向けたリスクコミュニケーションや防災教育の充実が図られます。
また、防災対策を推進した場合に見込まれる被害軽減効果の試算では、建物の耐震化や津波からの早期避難など、個人でも取り組める対策により、被害が大幅に軽減するとしています(図3)。
同ワーキンググループは、「自らの命は自らが守る」という意識の下、住宅の耐震化や家庭内での備蓄、迅速な避難行動に可能な限り取り組むことを求めるとともに、要支援者への体制も併せて構築する方針です。対策に取り組むことで被害は軽減できるとしており、同巨大地震から大切な人の命を守ることにつながることを期待するとしています。